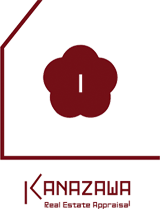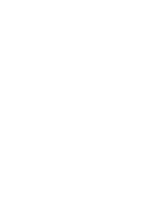2025.11.08 【研修】『不動産鑑定士としてこれだけは知っておきたい 宅地造成工事の基礎と小規模宅地造成工事の積算』『QGISを活用した不動産鑑定実務の効率化』
中国不動産鑑定士協会連合会主催の研修会に参加してきました!
会場は岡山県倉敷市の「倉敷アイビースクエア」です。

明治時代の倉敷紡績所(現クラボウ)発祥工場の外観や立木を可能な限り保存し、再利用して生まれた、ホテル・文化施設をあわせもつ複合観光施設で、2023年に先進7カ国(G7)労働雇用相会合が開催された場所です。


■ 第1部「宅地造成工事の基礎と小規模宅地造成工事費の積算」

まず第一部では、竹本朗先生による宅地造成工事の基礎と積算についての講義がありました。普段の鑑定実務の中で造成費を扱う機会は多いものの、ここまで土の性質や施工手順を体系立てて学ぶ機会はあまりありません。資料にもある通り、造成工事費は積算から請負金額に至るまでいくつかの段階を経て決まるため、単純に相場や経験だけで判断することはできません。土木工事標準単価や市場単価、施工パッケージ型積算など、根拠となる基準に沿って見立てることの重要性を改めて感じました。
特に印象に残ったのは、土量変化の考え方です。地山から掘削してほぐした状態、そして盛土として締め固めた状態で体積が大きく変わることは知ってはいたものの、それが実際の積算にどのように影響していくのか、資料で図示されていて非常に理解しやすい内容でした。造成地の評価を行う際に必要となる「切土と盛土のバランス」の考え方も整理され、より正確な見立てにつながると感じました。
また、調整池や沈砂池、水抜き孔など、防災を目的とした施設の理解も重要だと再認識しました。擁壁の背面に水が滞留することの危険性や、大雨時の排水経路の考え方などは普段の現地確認でも役立つ内容で、今後は水抜き孔の状態を以前より丁寧に確認しようと思います。
■ 第2部「QGISを活用した鑑定実務の効率化」

続く第二部では、西村研二先生によるQGISを活用した鑑定実務の効率化についての講義がありました。QGISは日常業務でよく使っていますが、まだまだ使いこなせていない部分が多いことを痛感しました。地理院タイルを利用した地図表示や、プロットのスタイル設定、定型図面の作成など、知っていれば大幅に時間短縮できる機能が多く紹介されていました。
特に、公図の公共座標系データを重ね合わせて航空写真と併用する方法は、現地調査の質を高める上で非常に有用だと感じました。山林や原野など、境界確認が難しい物件でも、事前に地図を作成しておけば調査がしやすくなります。また、KMLデータに変換してスマートフォンで確認できる仕組みは、実務でもすぐに取り入れられそうです。
さらに印象的だったのは、公示・調査の地点をQGISに取り込み、用途地域や小学校区と重ね合わせて一覧できる点です。地域的な傾向や土地利用の配置を視覚的に確認できるため、評価の説得力を高めるうえでも非常に有益だと感じました。
今回の研修を通じて、造成工事の理解もQGISの活用も、どちらも鑑定実務に欠かせない基礎であることを再確認しました。多くの気づきと学びが得られ、とても充実した一日となりました。
帰りに美観地区へ寄り道。







夜も素敵ですね✨✨
定番のきびだんごをおみやげに。

家に帰って、愛犬を家来に・・・