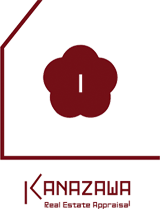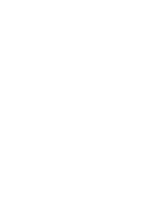2025.10.27 【研修】住家被害認定調査等研修会(水害編)
投稿時間 00:43
in 研修
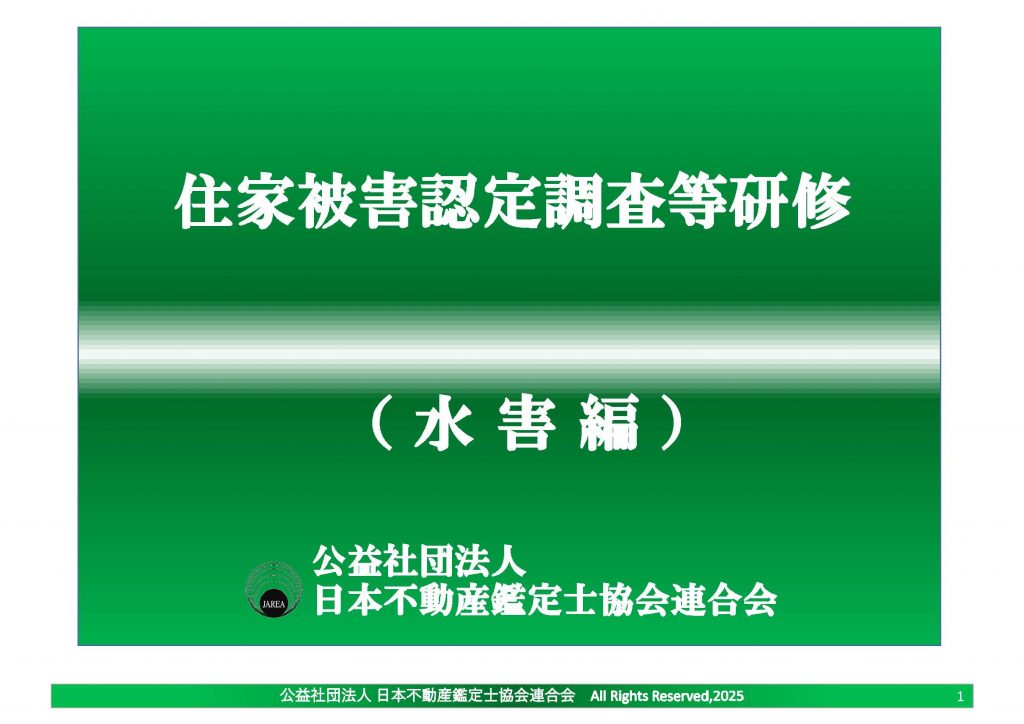
日本不動産鑑定士協会連合会主催の「住家被害認定調査等研修会(水害編)」を受講しました【オンライン研修】。
講師を務められたのは、令和6年能登半島地震の際に、現地で住家被害認定調査のご指導・ご支援をいただいた災害対策支援委員の先生方。私自身、能登での支援活動の中で大変お世話になった方々でもあり、今回の研修は学び直しと整理の機会にもなりました。
現場で役立つ「実践的な視点」
今回のテーマは「水害」。
地震とは異なる被害特性を持つ災害でありながら、被害の程度を適切に判定し、公平性・迅速性を担保するという点は同じです。
災害対策支援委員の先生方からは、
- 被害認定の基本的考え方
- 判定基準と調査票の書き方
- 木造・非木造・地盤の判定事例
- 調査現場での留意点やトラブル事例
などを、実務の視点で非常に分かりやすく解説いただきました。
「線引き」は冷たさではなく、公平性のために
講義の中で強調されていたのは、被害認定は被災者支援のためにこそ「公平性」と「正確性」を大切にしなければならないという姿勢です。
「同情や気持ちだけで基準を甘くしてしまうことは、一見やさしさのように見えても制度の信頼を損なう」という説明は非常に印象的でした。
能登での支援活動を通じてまさに感じてきたことです。
被災者の方の生活再建の第一歩である「罹災証明」は、公平でなければ信頼を失います。正確に判定することが、結果的に被災者支援になる――その原点を再確認する機会となりました。
能登の経験を次へつなぐ
能登半島地震では、私自身、多くの鑑定士・応援職員の皆様とともに住家被害認定調査に携わりました。
被災地の課題はまだ続いていますが、私たちの役割は「終わらせること」ではなく「次の災害に備えること」でもあると改めて感じます。
今回の研修で学んだことを石川県内の災害対応にも活かし、引き続き地域の防災力向上に貢献していきたいと思います。
最後に
講師の先生方、そして主催の日本不動産鑑定士協会連合会の皆さま、本日の貴重な機会をありがとうございました。