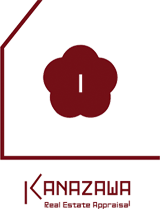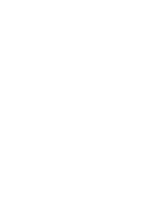2025.02.15 石川県の人口動態:年少人口の減少と進む高齢化
石川県は先日、昨年10月1日時点の年齢別推計人口を公表しました。そのデータから、県内の人口構成が大きく変化していることが改めて浮き彫りになりました。特に、0歳〜14歳の「年少人口」が11.5%と過去最低を記録し、65歳以上の「老年人口」は30.9%と過去最高になったことが注目されます。
人口減少と高齢化は全国的な傾向ではありますが、石川県内でも地域ごとに差が見られます。特に能登地域では、能登半島地震の影響もあり、若い世代の流出が進んでいることが示唆されています。石川県の人口動態の現状と、地域ごとの特徴について考えてみたいと思います。
❖ 石川県の人口推移と高齢化の現状

まず、石川県全体の人口は109万8,531人。このうち、年齢別の内訳は次の通りです。
年少人口(0〜14歳):12万4,459人(前年比3,718人減)
生産年齢人口(15〜64歳):62万695人(同6,191人減)
老年人口(65歳以上):33万2,990人(同1,134人減)
年少人口の割合は11.5%となり、前年から0.3ポイント低下。一方、老年人口の割合は30.9%で、0.2ポイント上昇しました。特に75歳以上の人口が19万4,321人(18.0%)と増えており、「超高齢化社会」が進行していることが分かります。
10年前の2014年と比較すると、年少人口は13.2%から11.5%に低下。一方で、老年人口は27.1%から30.9%へと増加しています。この傾向は県全体で見られ、かほく市を除くすべての市町で年少人口が減少し、老年人口が増加しています。
❖ 能登地域の高齢化が特に進行

特に高齢化が著しいのは能登地域です。奥能登(珠洲市、能登町、穴水町、輪島市)では、高齢化率が50%を超え、特に珠洲市は54.1%と県内最高の水準になっています。つまり、奥能登では住民の約半数が65歳以上という状況です。
この背景には、やはり能登半島地震の影響があると考えられます。被災後、若い世代が生活再建のために県外へ移住したことで、相対的に高齢者の割合が高くなった可能性があります。もともと能登地域は人口減少が続いていたエリアですが、地震によるさらなる人口流出が高齢化率を押し上げたといえるでしょう。
また、老年人口の増加に加え、生産年齢人口(15〜64歳)の減少も顕著です。県内で最も生産年齢人口が多いのは野々市市で65.4%ですが、最も低い珠洲市では39.3%と、大きな差があります。労働力の減少は地域経済にも影響を与えるため、人口減少と並行して課題となっています。
❖ 今後の課題と展望
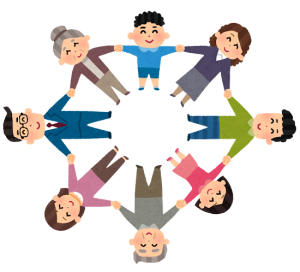
石川県全体で高齢化が進んでいるとはいえ、地域ごとに状況は異なります。野々市市や白山市のように比較的若年層が多いエリアもありますが、能登地域のように50%以上が高齢者となる自治体もあります。
高齢化が進むと、以下のような問題がより深刻化すると考えられます。
1. 医療・介護の負担増
高齢者が増えることで、医療や介護サービスの需要が高まり、地域の負担が増加します。特に能登地域のように医療機関が限られている場所では、適切な医療を受けることが難しくなる可能性があります。
2.地域経済の縮小
若年層や働き手が減少すると、地元企業の労働力不足が深刻化し、地域経済の衰退につながる恐れがあります。
3. インフラ維持の課題
過疎化が進むと、公共交通機関の運営が困難になったり、道路や公共施設の維持管理が難しくなったりすることが考えられます。
これらの課題に対し、行政や地域社会がどのように対応していくかが今後の重要なテーマとなります。例えば、移住促進政策や、リモートワーク環境の整備、地域資源を活かした産業振興などが求められるでしょう。
❖ まとめ
石川県の人口動態を見ると、年少人口の減少と老年人口の増加が顕著であり、特に能登地域では高齢化が急速に進んでいます。能登半島地震の影響も加わり、若い世代の流出が進んだ結果、奥能登2市2町では高齢化率が50%を超えました。
今後は、人口減少と高齢化がもたらす影響をしっかりと見据え、地域の活性化策や高齢者支援の充実が求められます。これからの石川県の未来をどう作っていくのか、一人ひとりが考えることが大切ではないでしょうか。
◇◆◇ 石川県での不動産に関するご相談、鑑定評価のご依頼は「株式会社かなざわ不動産鑑定」までお気軽にご連絡ください。tel 076-242-5420 ◇◆◇