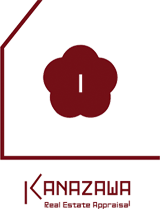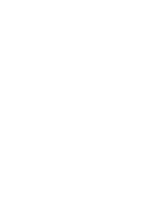2025.02.05 2024年の石川県の人口動向について
総務省の「住民基本台帳人口移動報告2024結果」が発表されました。石川県の人口移動に関するデータに大きな変化が見られました。特に、転出者数の増加と社会減少数の拡大が顕著となっています。
1. 石川県の社会減少が拡大
全国的にみると、社会増減(転入者数と転出者数の差、ならびに国外移動の差)によって人口が増加している都道府県が20県、減少している都道府県が27県ありました。
石川県は、前年に比べて社会減少数が最も拡大した都道府県となりました。具体的には、
- 転出者数:22,247人(前年比6.1%増加)
- 転入者数:18,071人(前年比2.4%減少)
- 社会減少数:2,275人(前年は161人の減少)
石川県は他の地域へ移動する人が増えており、流出が顕著になっています。
2. 転出超過数が大幅に増加
転入者と転出者の差(転出超過数)を見てみると、石川県は-4,176人で、前年の-2,461人から1,715人の増加となりました。これは全国でも大きな減少幅の一つです。
都道府県別のデータによると、石川県と同じく前年から転出超過が拡大した県は以下の通りです。
- 茨城県(+4,177人拡大)
- 石川県(+1,715人拡大)
- 愛知県(+116人拡大)
- 広島県(+698人拡大)
転出超過数の増加が示すのは、県外へ移住する人が増えているということ。これが一時的な現象なのか、恒常的な傾向なのかを分析することが今後の課題となります。
3. なぜ転出が増えたのか?
石川県の転出者数が増加した背景には、いくつかの要因が考えられます。
(1) 震災の影響
2024年1月に発生した能登半島地震、9月に発生した奥能登豪雨の影響で、被災地からの転出者が増えた可能性があります。特に能登地域では、住環境の悪化やインフラ整備の遅れにより、他の地域への移住を選択する人が増えたと考えられます。
(2) 大都市圏への人口流出
近年、東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)や大阪圏(大阪府・京都府・兵庫県)への人口流入が続いています。石川県からも、若年層を中心にこれらの都市部へ移動する人が多くなっていると考えられます。
(3) 産業構造の変化
地場産業の衰退や、働き口の少なさが影響している可能性もあります。特に、大学卒業後に県外で就職する若者が増えており、そのまま戻らないケースが多いことが指摘されています。
4. 今後の課題と対策
石川県の人口流出を抑えるためには、どうしたらよいのでしょうか。
(1) 震災復興と住環境の改善
被災地域への支援を拡充し、住環境の整備を早急に進めることが重要です。また、被災地に住み続けられるような仕組み(住宅支援・仕事の確保など)を構築することが求められます。
(2) 働き口の創出
若者が県内で働ける環境を整えるため、IT産業や観光業の振興、企業誘致などが必要です。テレワークの推進も、地方での生活を維持する手段として活用できます。
(3) Uターン・Iターンの促進
県外に出た人が戻ってくる仕組みを作ることも大切です。例えば、Uターン就職のサポートや、起業支援などを強化することで、県外からの流入を増やすことができます。
まとめ
2024年の石川県は、転出超過が大きく増加し、社会減少が拡大した年となりました。特に、震災の影響や大都市圏への流出が深刻な課題となっています。
今後は、住環境の改善、産業の活性化、Uターン促進など、さまざまな対策を講じる必要がありそうです。引き続き、県の動向を注視しながら、石川県の魅力を高めていくための施策を考えていくことが重要ですね。

◇◆◇ 石川県での不動産に関するご相談、鑑定評価のご依頼は「株式会社かなざわ不動産鑑定」までお気軽にご連絡ください。tel 076-242-5420 ◇◆◇